
・具体的な勉強スケジュールを考えて欲しい
・成果の出る勉強法をしりたい
上記お悩みを解決します。
本記事の内容
・宅建に合格した僕が、合格する勉強スケジュールを作ります。

宅建試験の勉強を開始したものの、
何から取り組めば良いか分からない。
参考書から始めたけど、問題が難しくて理解できない。
こんな方も多いのではないでしょうか。
実際に僕がそうでした。参考書を読んでるだけでは、一向に知識が深まることはなかったです。そうすると、こんな難しいならもうやめよ。となってしまいます。
今回はそんな僕が、どのように勉強のスケジュールを立て、取り組んでいたのかご紹介します。
【結論】過去問を毎日解く。これが正解です
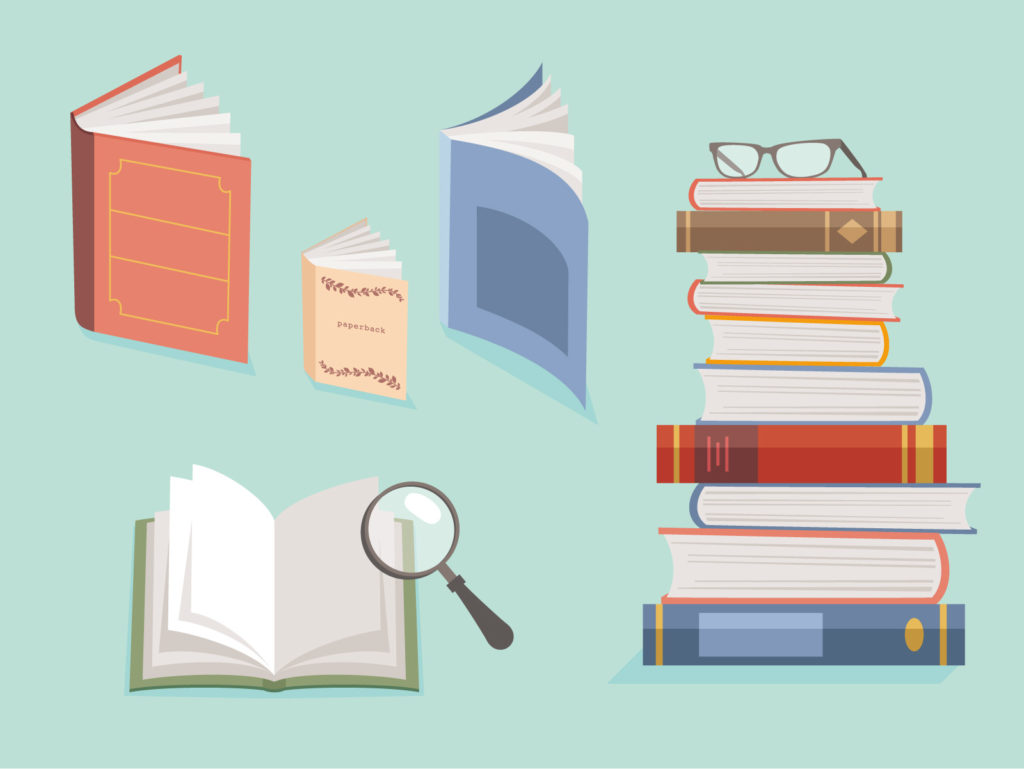
これが全てです。合格して改めて感じた事は、過去問対策が必須であるという事です。
【過去問は下記サイトから無料でDLが出来ます】

なので、過去問中心のスケジュールを組みます。
合格までの理想は、直近10年分の過去問を5週する事です。これが出来れば合格するといっても過言ではありません。
本試験の10月18日(日)から逆算し、過去問10年分×5回やりましょう。大変ではありますが、これをする事で合格出来ます。絶対にやりましょう。

例えば、試験日まで残り100日とすると、
1日の「過去問」勉強は問1~問25だけでOKです。
次の日に問26~問50まで解きます。
つまり2日で1つの過去問を完成させるだけです。
これで直近10年分×5週はクリアできます。
意外と簡単そうでしょ。過去問は一気に全問解くと疲れますよね。なので区切って勉強する事をおすすめします
ちなみに統計問題はその年の数字ですので解かなくて大丈夫です。
過去問を解く時間について


では、1つの過去問を2日で完成させるスケジュールで
勉強するとして、どのくらいの時間で解けばよいのでしょう。
宅建の試験時間は2時間です。
半分づつ解くので各1時間ずつ勉強すれば良いかというと、
そうではありません。
各30分~45分で解きましょう。理由は以下の通りです。
本試験では見直しの時間が必須。はやく解く練習をしよう
本試験では、最後に必ず見直しの時間を取らなければいけません。
これはケアレスミスを防ぐ為です。その為に過去問では早く正確に解く練習をしよう

ちなみに、過去問を解いた後は見直しの必要はありませんよ。
すぐに答え合わせをしましょう。
そこでケアレスミスが発生した場合は、次に気を付け、
ミスしやすいポイントを理解しましょう。
分からない問題を考える時間の排除。分からなければあとで勉強すればOK
過去問は自分の実力アップの為、本試験で合格する為に勉強するのです。

なので間違える事が合格への近道なのです。
間違えて、どこが違うのか答え合わせをする。そして理解する。
当たり前のこの流れが理解力向上への近道なのです。
過去問を解いて分からない問題は飛ばして、
次の問題にうつりましょう。
ちなみに、勉強を開始したばかりの時は、全問分からないという人もいるでしょう。その場合、全部飛ばしたら答えを見るだけになってしまいますね(笑)
それでも良いのですが、そういう方は、問題文を読み、よく分からんけど四択の中なら、これかな?みたいな感じで、選び自分の考えと合っているかどうか確認しましょう。
自分で考えて答える事で、その問題に対し「考える力」がつきます。ただただ惰性でボーと勉強するのと、考えながら勉強するのとでは、理解力に雲泥の差がありますね
短期的に集中し勉強する事で理解力が上がる。
過去問、過去問とこのブログでは伝えていますが、過去問を解く事は疲れます。
問1~問25のたった25問を解くだけでも、勉強をした達成感はすごいです(笑)
そんな過去問を解く作業に時間を掛けすぎると、一番肝心な答え合わせの作業がダラダラしてしまいます。
そうならない為にも、過去問を解くポイントは短期集中です。

そして答え合わせで最大の集中力を発揮しましょう。
短期集中で一気に解き、答え合わせに時間を掛ける。
理想の時間配分は25問の問題を解く事に30分、答え合わせに30分、
合計1時間のセットが理想ですね。
参考書の使い方はこうだ

参考書の使い方について解説します。
まずダメな例はこちらです。
・参考書の最初のページからひたすら流し読み
良い例がこちら
・過去問で間違えた分野を参考書で勉強
ちなみに、僕は宅建試験に4回も落ちています。その時の参考書の使い方は、最初のページからひたすら読書していました。
これをしていても、頭に入ってこないんですよね。特に民法などの苦手な分野は、目では参考書を読んでいるけど、頭では違う事を考えているなんてこともありました(笑)
参考書を読む事が無駄という訳ではありません。流し読みはそれで良いのですが、参考書への理解力を最大限にする為には、過去問で間違えた問題の分野をひたすら勉強する事が大事になります。
まとめ (未来問のご紹介)

最後に、僕が合格時に使って良かった、未来問をご紹介します。
未来問とは
資格大手サイトの「資格スクエア」が無料で提供している問題です。
宅建の過去問からAIが出題傾向を読み取り、今年出そうな問題集を作っています。これが【未来問】です。簡単にいうと、【予想問題】ですね。
興味がある方は下記リンクから未来問を入手できます。
AIが予測した宅建士試験問題、『未来問』無料プレゼント中 | 資格スクエア未来問について興味がある方は、こちらの記事に、未来問の解説を記載していますので、ご参考までに
過去問中心の勉強スケジュールを立てる事で、本試験の対策が可能です。過去問を解きまくり、間違えた分野を参考書で確認する。この流れが理想的ですね。
宅建試験開催も決定的ですので、まずは目の前の勉強を頑張りながら、本試験を迎えるようにしましょう!




コメント